ふたりのルール
朧影の月・月影の日――(現暦:4月17日)
今日もソニアは、朝からずっと恋愛シミュレーションゲームをプレイしている。
そして、ラムリーザは気づかれないように、ソニアの座っているソファーの後ろから見ていた。そんな彼に気づかないくらい、ソニアは熱中しているのだ。
よく見ると、ソニアはゲーム内で何かイベントが起きるたびにメモ書きをしている。そのメモに書かれていることを見てみると、やれ「電話ボックスで雨宿り」だの「膝の裏にキスをねだる」だの書かれていた。
それらはラムリーザにとって、何やら身に覚えのある内容だった。
「気になっていたから、しばらくそのゲームを見てたけどさ」
ゲームのエンディングスタッフロールが流れて、エピローグが語られる。もじゃもじゃ頭の女の子と、ハッピーエンドを迎えたようだ。
そこまで見終わってからラムリーザはつぶやいた。黙っていようかと思ったけど、あまりにも状況に問題があったためにそういうわけにはいかなくなっていた。
驚いたように振り返るソニアは、やはり見られていることに気づいていなかったようだ。
「ちょ、ちょっと、見ないでって言ったのに!」
「あのさ、ひょっとしてここ数日、そのゲームのイベントを現実でなぞってた?」
「え……、あ……、その……」
核心を突かれたのか、ソニアはあからさまに狼狽する。
「そこのメモ、『膝の裏にキス』とか書いてあるし、それこないだ僕にやらせたよな? まさか次はヘソにキスさせるとか言い出さないよな?」
「あぅ……」
ソニアは図星を突かれたのか、何も言えなくなってしまった。その様子を見て、ラムリーザはため息をついた。
「何がしたいわけ?」
「それは……、ミニゲームクリアして、そのご褒美に萌えイベントが起きるのよ。そしたら女の子との仲が良くなるのよ。だったらそれを実際にやったら、ラムも喜ぶんじゃないかなーって……ね」
ラムリーザにじっと見られて、ソニアはあたふたした感じで答える。目がきょろきょろしていて落ち着かない。喜ぶんじゃないかなと言っているが、残念ながらラムリーザはここ数日間ソニアの奇行に戸惑うばかりだった。
「それで、そのゲームの目的は何?」
ラムリーザは先ほどエンディングまで見ていたので、一通りは理解しているのだが、あえて問う。
「……告白して恋人同士になること」
ソニアは恥ずかしそうに目を伏せて、つぶやくように小さく答える。
「あのさぁ……」
ラムリーザは、再びため息をついた。
「告白したし、君も受け入れたじゃん?」
「え? あ……」
「お互いの親とも話をしたし、君とは結婚前提の付き合いをしているんだけどな」
やはり表向きに取り繕うとするためだけの告白になってしまい、付け焼き刃の関係にしかならなかったか……とラムリーザは内心舌打ちする。
「一緒に起きて、一緒に登校して、一緒に授業受けて、一緒に部活行って、一緒に音楽やって、一緒に下校して、一緒にご飯食べて、一緒にくつろいで、一緒に寝て、時々一緒に出掛けて」
ラムリーザはそこまで一気に言い、三度目のため息をついた。
「これ以上何が必要なんだ?」
「あぅ……」
とうとうソニアは俯いてしまった。
「君は何が不安なんだ?」
「だって……だって、リリスもユコもすごい美人だし……」
「…………」
「ラムが目移りするんじゃないかなって思って……」
やはりそうだったか、とラムリーザは一人納得した。そういえばソニアの様子が不自然になっていったのは、リリスとユコの二人と知り合ってからだったと思い返す。そして理解した。勝手に一人で嫉妬して不安になって暴走していたのだな……と。
「確かに君の言う通りあの二人は美人だ。だがな……」
ラムリーザは、ソファーに座っているソニアの隣に移動して肩に手をやって言葉を続けた。
「君もあの二人に劣らず可愛いよ」
「で、でも……」
「僕がそう言ってるんだけど、信用できないのかな?」
「…………」
ソニアは伏せた目から涙がこぼれた。
「ごめん……ね」
「ほんと、しょうがないな君は」
「あのね、ラム……」
少し間を置いて、ソニアは迷うような仕草を見せておずおずと尋ねた。
しかし何かを言い出したいけど、言えないような感じだ。
それでもしばらく迷った後で、口を開いた。
「ラムは、どうしてあたしのこと好きなの?」
そう言ってから、聞いてしまったとでも言いたげな顔をする。
ラムリーザは「ん?」と思った。まだリリス、ユコ不安が解消されていないのか? と。
だから、安心させるために優しく語った。
「そうだなぁ、君といるのはもう当たり前のことで、自然なこと。ただ、その当たり前を壊したくないから、こうして一緒にいる。あれ? これは好きな理由になるのか?」
ラムリーザは言ってみてから改めて考えてみる。どうして好きなのだろうかと……。
顔か?
いや、顔で選ぶなら、リリスやユコでもいい。
ならば何だ?
ソニアの特徴と言えば、大きな胸だ。
だが、胸が大きくなる前からも一緒にいた。
そして、胸が大きくなったから好きになった、という感情はなかった。
大きくなる前も、大きくなった後も感情は変わっていない。
ならば、健康的な脚か?
いや、脚が好きだというのも変な話だ。
そもそも、こうして寄り添って立っていることが多いから、脚は視界にほとんど入らない。
緑色が好きなラムリーザだ。
そして、ソニアの髪の色は青緑色である。
それがいいのだろうか? と思うが、決定打としては弱いと思う。
髪が青緑色だから好きなのか? と言われたとしても、そうだとは即答できないだろう。
たとえソニアが金髪だろうが、黒髪だろうが、変わりないと思う。髪の色など、記号でしかないのだ。
そもそもラムリーザは、ソニアに対してわかりやすい女の形というものを求めていなかった。
料理は料理人が作り、掃除、洗濯、裁縫などはメイドがやってくれる。そういう環境でこれまで生きてきたのだ。
結局のところ、結論が出せなくなってしまい、
「理由はわからん。わからんが好きだ。君といると楽しいし、君がいないとつまらない」
そう答えるしかなかった。
それを聞いたソニアは、好きだと言ってくれたことで、少し嬉しそうな顔をした。
だがもう一度聞いた、今度は少し言葉を変えて。
「あたしのどういったところが好きなの?」
妙に深掘りしてくるな、とラムリーザは感じた。だが、深く考えたこともなかったので、今日みたいな日にはじっくり考えてみるのもいい気がした。
どういったところか……。
ソニアはとにかく可愛いのだ、とラムリーザは真っ先に思った。
美味しいものを食べるときの幸せそうな顔、何か買ってあげたときの喜ぶ顔、ゲームをやっている時の楽しそうな顔、夜腕の中で寝ているときの安心しきったような寝顔。
何もかもが可愛かった。
そういったわかりやすい感情表現が好きだった。
また何か食べさせてあげよう、何か買ってあげようという気になれるのだ。
「…………」
頭の中には思い描いていたが、この時は言葉にはしなかった。
黙っているラムリーザを見て、ソニアは恐る恐るといった様子で聞いた。
「じゃあラムがあたしにこうなってほしいっていう要望はある? こんな女になってほしいとか……」
最後に付け加えた言葉は小声になっていた。
それに関しては、ラムリーザは常日頃から思っていることを素直に言った。
「僕はソニアに幸せになってほしいと思っているんだ」
ソニアは満面の笑顔で答えた。
「うれしい……ありがとう」
そう言って、ラムリーザの胸に飛び込んできた。
ラムリーザはソニアをしっかりと抱き寄せ、唇を合わせた。
もう一度やり直しだ……と言わんばかりに。
唇が離れたあと、ラムリーザは額を軽く合わせ、息の熱が混じる距離で言った。
「じゃあ、『これからを間違えない』ために、今日からのルールを作ろう」
ソニアがきょとんとして頷く。
「まず一つ目。嫉妬や不安を感じたら、イベントで埋めない。言葉で言う」
「……言う、わかった」
「二つ目。週に一度は『電源オフの日』を作ること。できればゲームを閉じて、二人で散歩か、曲作りをする」
「曲作り?」
「うん。軽音でやる最初のオリジナル。タイトルは例えば……『電話ボックスの雨宿り』なんてどうかな?」
ソニアがふっと笑って、目尻の涙を指で拭った。
「ラムずるい、さっき文句言ったことを曲にするの。でも面白いかも、あたしはあれ楽しかったから」
「三つ目。合図を決めよう。心が揺れた時は、こう」
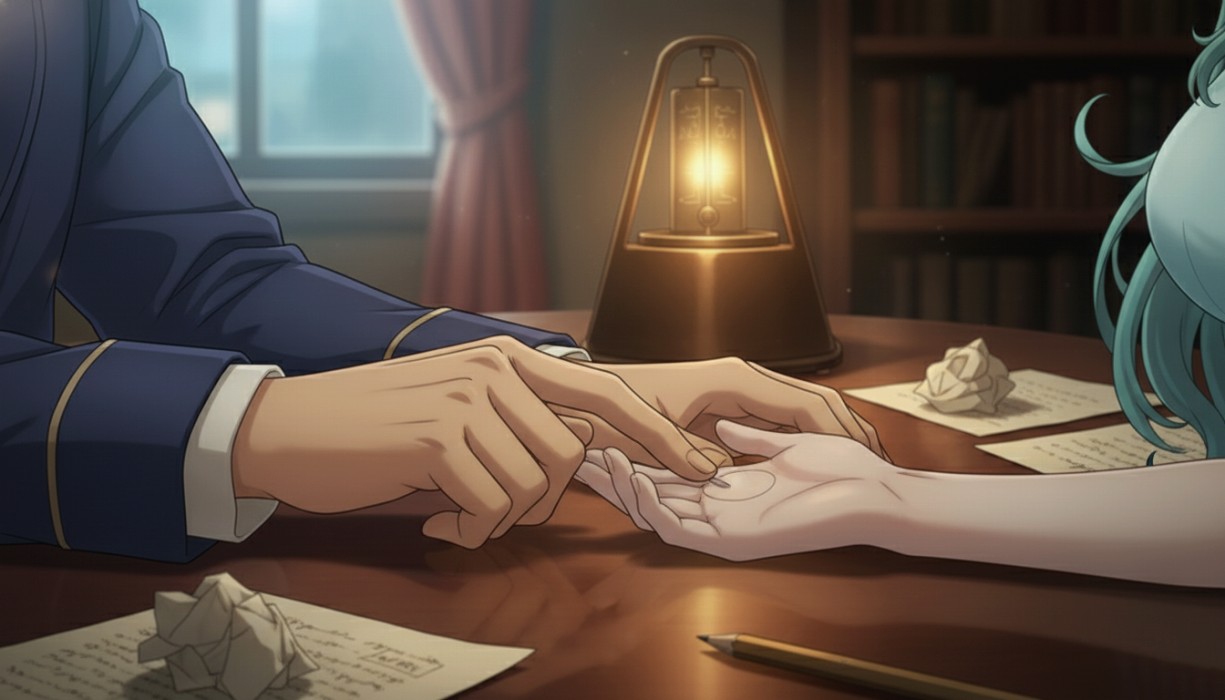
ラムリーザはソニアの手のひらに、自分の人差し指で小さく円を描く。
「『ここにいる』の合図、二人が迷子にならないために」
ソニアは掌をぎゅっと握りしめた。
「わかった。じゃあ、あたしからも一つ。『評価基準をラムにしない』。ゲームの選択肢じゃなくて、ラムの顔を見て決める」
「いいね、採用」
二人で窓を開けると、夜の空気が柔らかく入り込む。山風がカーテンを押して、紙片をふるわせた。ソニアのメモがふわりと舞い、ラムリーザは拾い上げて机に閉じ込める。
「これはもう封印だね。代わりに、こっち」
メモの別ページに五線譜を書き込み、最上段に日付と町の名、それから二人の名前を書き込む。
「ドラムは素でいける。ベースはソニア。イントロは雨粒、間奏で山風。歌詞は、なんだろうねぇ」
ソニアはベッドの下から新品のメトロノームを取り出した。これは先日、ラムリーザが日用品の買い出しに行った時についでに買っていたものだ。
「進める、ってこういう意味でしょ?」
「そう、バンドを、そして関係や生活を」
軽くテンポを合わせ、机をスティックで叩く代わりに鉛筆の尻で刻む。コツ、コツ、コツ。ソニアの指がテーブルで低いルート音をなぞり、ふたりの呼吸が拍の隙間でそろっていく。
「ねえラム」
「ん?」
「『当たり前を壊したくない』って、さっき言ったよね。だから壊さないために、増やしていこう。当たり前を」
ラムリーザはうなずく。
「毎週一曲分の『当たり前』。失敗したら笑う、うまくいったら録音する。生徒会で先輩がいなくても、僕らは始められる」
窓の外で、遠く雷鳴が小さく転がる。ふたりは顔を見合わせて笑った。
「ラム、エンディングは?」
「まだ要らない。セーブして、続きから――かな?」
「どこでセーブするの?」
メトロノームを止めると、部屋は静かになった。ラムリーザは明かりを少し落とし、ソニアの両肩を包む。抱き寄せる腕に、約束の重みが宿る。
「ベッドでセーブ。おやすみ、ソニア」
「おやすみ、ラム。明日は『電源オフ』ね」
返事の代わりに、もう一度だけ短いキス。